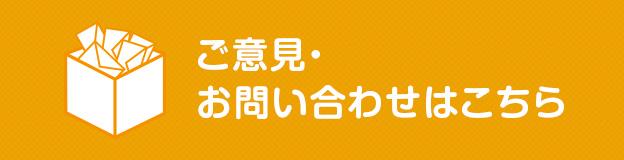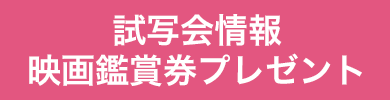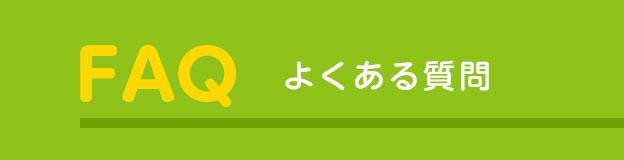SPECIAL
原作・脚本 清水有生さんインタビュー*後編*
「さくらの親子丼」シリーズの台本を手がけている清水有生さん。清水さんがこの作品に込めた思いを伺いました。さらに、世間的にはまだあまり知られていない子どもシェルターを題材にした経緯なども語ってもらいました。前後編に分けてご紹介します。
清水有生さんインタビュー後編です。若手メンバーの印象や、最終話の見どころなどを語ってもらいました。

- さくらは前回とまったく違うシチュエーションに立ちました。第2弾のさくらをご覧になっての感想は?
- 視聴者のみなさんの中には、前回と変わらない場所で葛藤したり、奮闘したりするさくらを見たいという方もいたと思います。僕自身としては、新しいキャラクターが訪ねては去る展開だと、さくらと一人ひとりが心を通わすまでを早い展開で描かなくてはいけないのが心残りだったんです。
今回はよりホームドラマ感を出したくて、基本的にはさくらを決まった場所から動かないようにして、それぞれの人物とじっくり向き合う話にしました。皆が同じセットで演技をするから、自然と関係が深まります。後半は信頼関係があるからこそのシーンが散りばめられていて、最終回では川端(柄本時生さん)と鍋島(相島一之さん)がふたりで語り合う場面を用意しました。7話までさまざまな出来事を経てのふたりだから成立するシーンになっていると思います。僕も気に入っている場面なのでぜひ見ていただきたいです。
- オーディションで選ばれた若手メンバーはいかがでしたか。
- それぞれ役のことを真剣に考えてくれたと思います。撮影に入る前、皆と会う機会があり、「役の設定を教えてください」と質問されました。僕の話を聞いて、役作りの参考にしたかったのだと思います。でも僕は「役の細かい設定も、先の展開も気にしないで演じてほしい」と伝えました。
いま、ドラマや映画って漫画や小説など原作があるものが多いし、原作があると確かに演じるヒントを見つけやすいです。そのヒントをもとに、自分なりに役作りをするのが役者の仕事と思いがちだけれど、役作りに限度なんてないんです。それなら、ヒントがない中で考えに考えて、もしかしたら最後まで答えは見つからないかもしれないけれど、演じ終わったとき、「もしかしたら、こうだったのかも」という程度のものを感じられればいいんじゃないか、と僕は思っています。
- 現場では、若手のみなさんが懸命に役と向き合う姿が印象的でした。
- 皆どんどん良くなっていきました。もともとオーディションのときからレベルが高いと思っていたんです。由夏(岡本夏美さん)なんて、部屋に入ってきた瞬間から戦う気満々で。あれは彼女の作戦だったのかな?(笑)詩(祷キララさん)も、「詩はこの子だな」と思わせる佇まいを最初から見せていました。
皆、それぞれの役をどう演じようか悩んでいて、香(塩野瑛久さん)には、子どもたちは全員大人のことを嫌っていて、香もそうだけれど、母親への思いは残っていると話したんです。だからさくらに母親を重ね、慕うのだと伝えました。
- 若手キャストのみなさんに話を聞くと、実はそれぞれのキャラクターの心情が詳しく描かれていなくて難しいと、一様に言っていました。
- 子どもたちがシェルターにいられるのは、せいぜい2カ月。さくらと出会ったからといって性格や生き方が急に変わるわけがないし、問題が解決したり、完結したりするはずがないんです。子どもシェルターでどんなことを感じるのか、それぐらいのことが描ければいいと思っていました。メンバーの中に演技経験の浅い子を選んだのは、演じる子自身がそのときどき、どんなことを感じているのか演技にダイレクトに出してほしかったからです。

- 若手キャストのみなさんの意見でもうひとつ。物語が深刻とはいえ、演技自体は重いものにならないよう、心がけることを求められたとのことでした。
- それは僕が見聞きしたものが影響しています。更生施設出身の若者と話したことがあるんですけど、みんな礼儀正しいし、明るいんですね。それによく気も利くんです。誰もが大変な過去の持ち主で、ちょっとでも問題を起こすとすぐ悪く言われてしまうから、日頃から徹底的に明るく、笑顔を絶やさないよう心がけているそうです。でも、どんな場所でも楽しいことってあるし、そこで自然と笑いが起こることもあるはずです。そういうところもリアルに描きたかったし、一方で、その笑顔や明るさはどこか切ないんですよね。
- 「さくらの親子丼」シリーズは“食”、食べることが重要なモチーフです。その意図は?
- 僕はドラマにおいて、食事の場面って重要だと思っています。今回は心に傷を負っている子たちの話なので、食事のシーンも和気あいあいとはいきませんでしたが、第2話でおでんを食べましたよね。それもしゃべるのを忘れるほど無我夢中で。セリフなんてなくても、食べる姿を映すだけで伝わるものがあるんです。
作り手の中には、ただ食べるだけの場面は映像としてもたないと思う人がいるんですけど、食べる姿に説得力があれば、食事のシーンでいくらでも見る人の心を震わせる場面が生まれるはずなんですけどね。
- 改めて清水さんが「さくらの親子丼2」を通して、伝えたかったこととは?
- 第一は「子どもシェルター」の存在を広く知ってもらいたい、というのが大きいです。問題を抱えた子どもたちがどうすれば社会の中で存在していけるのか、考えている大人が大勢いるんです。でも、その人たちの思いがなかなか実らない。そういう現状が確かにあります。
子どもシェルターに加え、施設にいた子たちが身を寄せる自立援助ホームという場所もあります。寮のようなところで、親代わりのような人もいるし、若者がここで暮らしながら勤め先に通います。自立援助ホームは地域に受け入れられていて、周囲の人々も一緒に若者を育て、若者も地域の活動に力を入れ、懸命に生きているケースが多いと聞きました。ところがこういった施設もまったく数が足りなくて、入居待ちの若者がたくさんいる状態です。いまの社会が、こういった問題を抱えていることを知っていただきたいです。
またドラマとして、この作品は派手さはないかもしれません。でも、視聴者のみなさんの中には、重厚な小説を読むかのごとくじっくり人間ドラマを見たい、という方がいるはずです。そういう方々に向け、「さくらの親子丼」シリーズを生み出したつもりで、思いの外たくさんの支持を受けたことに感謝しています。これからもこういった作品をぜひ届けていきたいです。
- 最後に、最終回の見どころをお聞かせください。
- 同じことの繰り返しになりますが、「子どもシェルター」は避難している子どもたちにとって、“通過点”でしかありません。ここからどこに向かっていくのか、希望を感じる者もいれば、まだまだあやふやな者もいるし、厳しい現実を突きつけられる者もいるでしょう。どうすれば彼らが社会に受け入れられるのか、見てくださるみなさんが考えるきっかけになれば、と願い最終回を書きました。何かを感じ取っていただけたら幸いです。
子どもたちだけでなく、さくらが「子どもシェルター」での経験で何を得るのか、どんな道を進んでいくのか。さくらの選択にも注目してほしいです。