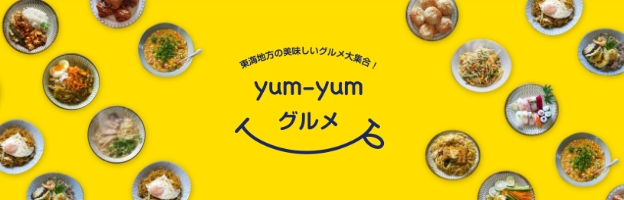チーズの消費量が右肩上がりに増えているが、国産チーズの割合は13.7%で、ほとんどが輸入物だ。岐阜県高山市で国産チーズを広める取り組みをしている男性がいる。「地産地消」のモッツァレラチーズ作りに取り組んでいる男性を取材した。
■子供の病気がきっかけで故郷に…飛騨高山の魅力活かす“異色のチーズ職人”

岐阜県高山市の「トリデンテ」は小さなチーズ工房だ。
【動画で見る】輸入物は価格不安定で環境負荷も大…プロの料理人も評価する“地産地消”のモッツァレラチーズ 国産チーズの未来

伊東聖晃(いとう・まさあき 46)さんは13年前、独学でチーズ作りを始めた。

午前10時半。搾りたての生乳(せいにゅう)800キロを、温度管理のできる「チーズバット」に貯めるところから伊東さんのチーズ作りは始まる。

伊東聖晃さん:
「飛騨という環境が、乳質・乳の質を上げるのにとってとてもいい環境であるということと、生乳を生み出すには寒冷なところがいい、乳脂肪率が高くなるので」

生乳は、乳の成分を壊さないよう、すぐに63度から65度の低温で殺菌。その日の気温や天候に応じて温度を調整する。
伊東さん:
「乳酸菌を入れたことで発酵がスタートしたので、ここから温度管理と時間管理が非常に重要になってきます」

大学で物理学を学んだ伊東さんは、実験と研究を繰り返し、独自のレシピを作った。
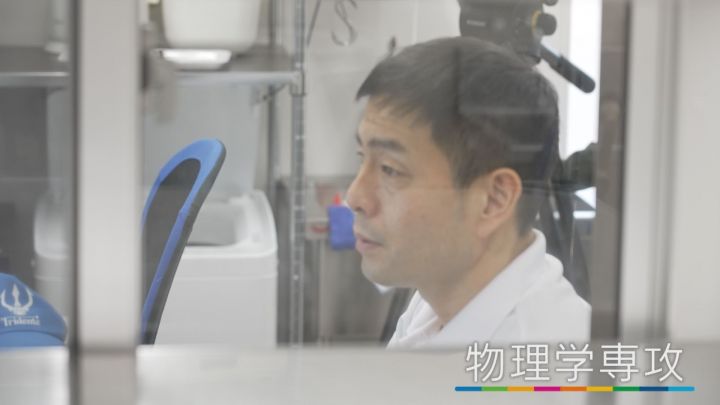
美味しいチーズを作るコツは、ここからの時間管理と温度管理だ。
伊東さん:
「自分でレシピを数値化して、時刻を入れると、その日のタイムスケジュールが出るようにしてあります」

伊東さんは岐阜県高山市の出身で、東京の大学へ進み、卒業後は会社を経営していた。

ところが、幼稚園児だった子供が重度のアトピー性皮膚炎になり、空気と水が美味しい地元の高山市に戻ることを決めたという。

高山市で起業することになり、地元の資源を活かせる仕事がしたいという思いから、地元の牛乳を使った“手作りのチーズ”を手がけることに決めた。

仲間3人と立ち上げたのが、トリデンテだ。
■切るとミルクがあふれ出す…朝から10時間かけて作る「モッツァレラチーズ」

午後5時、生乳が固まり始めた。伊東さんは目の粗い網で生乳を切りながら、「今はもう、全体が杏仁豆腐のようになっている」という。

そして間もなく、混ぜ始めた。
伊東さん:
「だいぶ水分と固形分のバランスが変わっているのがわかると思います。(水分が)抜けてきましたね」

固まった部分をすくい上げる。

チーズを作る過程で出る大量の“上澄み液”。乳脂肪分やたんぱく質を除いた液体で、これをホエーという。

生乳のうち9割が“ホエー”となり、通常は廃棄物として処理されるが、トリデンテでは、できるだけ捨てない工法を開発した。また余ったホエーは、別のチーズの原料になる。
午後7時。固まった生乳を5度の氷水につけて、発酵を止める。

10分後、今度は90度の熱湯に入れて、チーズを成型。表面を撫でてツヤを作ると同時に薄い膜ができ、ミルクを閉じ込める。

伊東さん:
「もともとイタリア語で『引きちぎる』っていう意味があって、まさに今やっている作業がモッツァレラの語源になっていますね。ここを頑張れば頑張るほど、ミルキーなチーズができるので…」

午後9時半。450個のモッツァレラチーズが完成しました。朝から10時間の作業です。

伊東さん:
「(半分に切って)すごくいいですね。だいぶ秋も深まって、乳脂肪率が高まってきたんだと思います。モッツァレラがおいしい季節になりますね」
あふれ出るミルクはフレッシュなチーズの証だ。

100%飛騨の牛乳で作るモッツァレラチーズ「トリデンテ」(125グラム650~700円)。

プロの料理人も絶賛する。
■国産チーズへの追い風…コロナ禍で消費量増加も輸入チーズは価格や環境面の負担大

伊東さんには、全国から注文が入る。顧客はプロの料理人だ。

伊東さん:
「(取引先は)たぶん100店舗超えてくると思うんですけど…。プロの仕様に耐えられる、プロの人が使って遜色ないものを作りたいというのは創業当初からあったので」

高山市のレストラン「フォルケッタ」は、以前はイタリアからの輸入モノを使っていたが、地元のトリデンテのチーズに切り替えた。

レストラン「フォルケッタ」のシェフ:
「イタリアから空輸で来るんですけど、どうしても少し日数が経つのと、地元のものだと今日作ったものが届くという、フレッシュさが全然違う。普通のチーズって熟成させて美味しいけど、モッツァレラってフレッシュな時がおいしいもんだから、その辺は地元で作ってもらっているメリットは大きい」
名古屋市熱田区の高級スーパー「サポーレ」でも取り扱われていた。

「サポーレ」では、フランス、ドイツ、イタリアといったヨーロッパ中心に、世界中から400種類の厳選した輸入チーズを扱っているコーナーもあるが、今、国産チーズにも注目していた。

スーパーサポーレの店員:
「ウクライナの戦争で飛行機のルートが不安定ですね。ヨーロッパ全体からの空輸が、ウクライナ上空を飛んでいて、余分に日数がかかっています。イタリアのフレッシュのモッツァレラが特に影響受けていますね。4~5割(価格が)上がっているのが現状です。荷物がきた時に入っていないって…そんな状態です」
コロナ禍の“家飲み”需要もあり、チーズの消費量は右肩上がりとなったが、8割が輸入商品だった。

輸入チーズは価格が不安定で、輸送の際、環境への負荷も大きくかかる。
チーズプロフェッショナル協会の担当者:
「当然、牧場とチーズ工房が近いに越したことはないし、絞ったミルクを短時間でチーズにする技術も必要だし…。年間でチーズの消費量って35万トンくらいあるんです。純国産と言われるのが、2万7000トンくらいなので、誇れるほどの量を作っていないんですね。本当にわずかですね」
■地元のチーズ発信する工房増えてほしい…飼料高騰や後継者不足等の逆風も

伊東さんは、チーズ作りのノウハウを『モッツァレラチーズ製造実践ガイド』という冊子やWEBページで無料で公開している。

伊東さん:
「僕が最初始めるときに、なかなか情報がなくて苦労したっていうのがあって、これから始める人のとっかかりになればいいかなと。どんどん国産に乗り換えてもらう、きっかけづくりの方が大事だと思っています」
伊東さんはさらに国産チーズのすそ野を広げるため、生乳の温度管理をする「チーズバット」を開発した。

伊東さん:
「うちのチーズバットは、家庭用の給湯器でも温度管理できるところが特徴ですね。ここの部分が二重構造になっていて、お湯が循環するようになっています」

これまで500万円以上もする大手メーカーの商品しかなかったが、伊東さんは格安で提供している。国内のチーズ工房は約300件。これまで20件近くの工房をサポートしてきた。

伊東さんが考える、チーズの未来は…。
伊東さん:
「せっかくいま国産チーズに追い風になっていて…。ただ生乳を取り巻く環境っていうのは、飼料が高騰していたりとか後継者不足だったりとか、いろんな逆風が吹いているのも現状としてあるんですよね。チーズ作りがもっと国内で活発になって、そういう受け皿になってくれればいいなと思います。地元のチーズを発信するような工房が増えてくれば、いろんな地域にとってもメリットというかハッピーになると思いますので。そういう未来がうれしいですね」
2022年12月8日放送