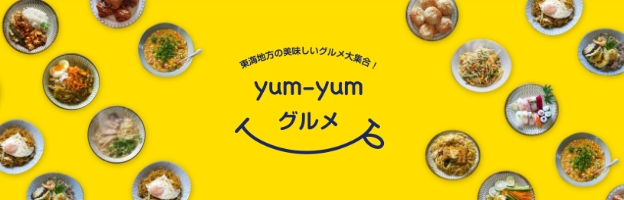ものづくりがさかんな愛知県では、伝統守り続けてきた老舗もあります。愛知県常滑(とこなめ)市の「山源陶苑(やまげんとうえん)」は常滑焼の窯元で、市内では唯一、常滑焼の起源である「かめ」を作り続けています。経営者の母親がこの「かめ」を使って作る限定の「かめパン」が人気を呼んでいます。
■常滑焼の起源「かめ」の製造を作り続ける窯元「山源陶苑」
常滑市の「山源陶苑」は、日本六古窯(ろっこよう)の1つ、「常滑焼」の窯元として、1967年(昭和42年)に創業しました。
【動画で見る】伝統の「かめ」で作った”母のかめパン”が大人気…日本遺産の焼き物・常滑焼の窯元が始めた新たな一歩

現在は、3代目の鯉江優次(こいえゆうじ)さんと、弟の應臣(たかおみ)さんが中心となって、壺、土瓶、器など、およそ150種類の常滑焼を生産しています。

また、陶芸体験教室を開くなどして、常滑焼の魅力を若い世代にも伝えています。

900年の歴史を誇る「常滑焼」の起源は、食料の保存容器として作られた「かめ」でした。

「かめ」は、最盛期は6~7軒の窯元で作られてきたものの、時代とともに減少し、いまは常滑市では山源陶苑1軒のみです。
地元の土を成型して釉薬をつけ、1180度の窯でおよそ9時間、伝統の製法を守っています。

山源陶苑の3代目 鯉江優次さん:
「その昔は知多半島に200軒の酒蔵があったりとか、今は6軒になっちゃったんですけど。あと、味噌。武豊のほうの豆味噌だったり、たまりしょうゆだったり、みりんだったりっていうのは大体常滑から30分圏内くらいで、実をいうと発酵っていうのがベースである食文化がすごく盛んなんです」

常滑焼は温度変化に強く、吸水性が低いのが特徴です。「かめ」は、味噌や酒などの発酵食品や梅干し作りに重宝され、食品の保存にも使われてきました。
■伝統の「かめ」を活用した新たな一手は“パン作り”
山源陶苑は、その「かめ」を使ってパン作りを始めました。

商品名もそのまま「かめパン」(800円 かめ付き)で、ぷっくりと膨らんだシルエットがかわいいと人気です。

山源陶苑は直売所の「TOKONAME STORE(トコナメストア)」も運営していて、かめパンをはじめ、常滑焼の器や「かめ」などを販売しています。

かめパンの販売は土・日・祝日だけで、1日30個限定です。このパンを求めて、市外から来るお客さんもいました。

愛知県岩倉市から来た女性客:
「去年買ってすごいおいしかったので。子供たちも気に入って」
愛知県美浜町から来た女性客:
「柔らかくて、食感がすごいモチモチで本当においしい。最初食べたときに感動して。リピーターです」

「かめ」から引っ張り出すと、きのこのようなかわいい形で、しっとりとやわらかくふかふか。バターとのあまじょっぱさが絶妙です。

常滑焼の「かめ」で焼くことで、「熱がゆっくりと伝わるので、しっとりする」と鯉江さんはいいます。
■リユースの象徴に…「かめ」は調理器具として使うことも
食べた後の「かめ」は、調理器具として使えます。常滑焼は鉄分を多く含んだ土を使っていて、遠赤外線によるゆっくりとした熱伝導で、しっとりとふわふわに調理できるといいます。

山源陶苑では、その特徴を生かした「かめ」料理のレシピをインスタグラムで発信しています。さつまいもを使った蒸しパンや、いちごを使ったマフィンなどが評判で、今では50種類以上になりました。

また「かめ」が不要になった場合には、1個100円で買い取りも行っています。
鯉江さん:
「僕ら的には新しいものが売れた方が当然ありがたいですけれど、そういうところじゃなくて、有限な資源なんだよっていうのを知ってもらったりとか、資源を常にずっと使ってリユースし続けるみたいなそんな仕組みにこれを持って行きたい」
■「かめパン」作りのきっかけは“父の死”
「かめパン」を作ったきっかけは、鯉江さんの父、康司さんの死でした。「かめ」の伝統を守っていきたいと考えていた矢先のことで、母、裕見子さんが塞ぎがちになったのを見て、昔を思い出したといいます。

鯉江さん:
「父と母がずっと二人三脚で工場で働いていた。父が亡くなって、母が引退して家にこもってしまった。まあこもってというか、家にいがちになった状態になってですね。その中で僕が小さいころにパンをよく作ってくれていたのを思い出したので、母親にそういう話をして、『よかったらやらんか』みたいな話からスタートしていった感じです」
「かめ」の伝統を守っていきたいと考えていた矢先、鯉江さんの父・康司(こうじ)さんが他界。ふさぎがちになった母親を見て思いついたのが、かめでパンを作ることでした。
鯉江さんの母 裕見子さん:
「陶芸を作るときの工程とよく似ていて、触った感じとか。同じ延長線でやっているような感じです」

家族を思う気持ちが「かめ」の新たな活用法に繋がっていました。
2025年2月13日放送