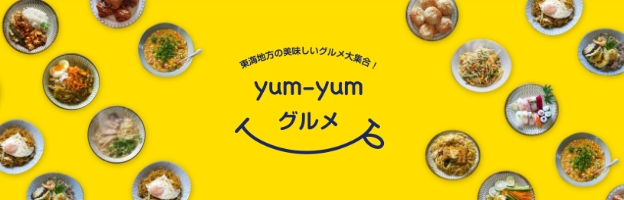南海トラフ地震で発生する津波から命を守るため、浸水範囲をシュミレーションする研究に注目が集まっている。デジタルツインと呼ばれる「現実世界のコピー」を活用し、災害リスクを「見える化」することで、市民の防災意識の向上につながることも期待されている。
■津波から命を守るシステム“デジタルツイン”とは
近い将来の発生が懸念される南海トラフ巨大地震は、最悪の場合、死者は32万3000人と、東日本大震災のおよそ16倍にも及ぶとされる。
特に被害を甚大化させるといわれるのは津波で、震源が陸地に近く、あっという間に津波が押し寄せると想定されている。
【動画で見る】「どこまで逃げないと危険か」も瞬時にわかる…防災に活用される『デジタルツイン』現実世界のコピーで津波等の被害を“見える化”

津波から1人でも多くの命を救うために開発されたシステムが、宮城県の東北大学にある。
東北大学 災害科学国際研究所の越村俊一教授:
「仮想世界での様々な検討・実験の結果に基づいて、物理世界でどういう風に対応したら、我々にとって一番いいのかということを探る。それが『津波災害デジタルツイン』の本質的な機能です」

『デジタルツイン』とは、現実世界の地形や形などをデジタル空間上で双子のように忠実に再現した仮想世界で、“現実世界のコピー”を作ることで、未来をいち早く予測するという。

越村教授の『リアルタイム津波浸水被害予測システム』は、地震発生時に震源や規模・地殻変動データなどを自動で取り込み、「地震が起きた世界」をコピーする。

これまで数日はかかっていた津波の被害予測が、あっという間にできるという。
■迅速に被害予測を算出…「日向灘地震」では実力を証明
デジタルツインの実力が発揮されたのが、2024年8月に発生した日向灘地震だ。

宮崎県などに津波注意報が出され、運用開始以来初めて、南海トラフ地震臨時情報が発表される中、発生およそ20分後には「浸水や被害はない」と予測していた。
実際に宮崎港で0.5mなどの津波が観測されたものの、大きな被害は確認されず、精度の高さを証明した。

越村教授:
「たとえば夜中に津波が起きた、あるいは朝早くに津波が起きた。様々な条件を設定して仮想世界の中で訓練とか実験ができる。これは現実世界ではとても無理ですよね。多くの方が東日本大震災で亡くなりました。津波がどこまでやってくるのか、そして、どこまで逃げれば安全なのかということを伝えることができれば、救える命は必ずある。そのために津波の高さの予測だけじゃなくて、津波の浸水範囲がどこまで広がるのかということを、予測する必要があると思うんです」
この予測システムは、南海トラフ地震に備える高知県庁でも導入され、2024年2月には、大規模訓練が実施された。

『デジタルツイン』は想定したデータをもとに“地震発生”からわずか18分で予測を叩き出した。

起きてみないとわからない被害の全容をシミュレーションすることで、早い段階から具体的な救助プランなどを検討できるのもメリットだ。
■地震以外の災害時にも…「盛り土」の存在も指摘
『デジタルツイン』が役立つのは津波被害だけではない。28人の犠牲者を出した2021年7月に発生した静岡県熱海市での土石流災害でも成果を出した。

崩れた地形の正確な把握に、すでに県内で進めていたデジタルツインが活用され、本来1~2カ月はかかるはずの土砂の測量を、1週間程度で実施できた。

さらに過去に遡って地形を比較し、原因が盛り土にあることも突き止めた。

静岡県は2024年1月の能登半島地震でも、300キロほど離れた被災地、石川県のデータを取得し、発災当日から復旧に向けて被害状況の把握に着手した。デジタル空間での解析のため、どこにいても作業ができる。

静岡県デジタル戦略局の担当者:
「遠隔地で被害の少ないところの方々がデータを可視化してくれたものを我々が見て、フィードバックしていただけるような環境が必須だと思っている。データを遠隔でそれぞれみんな使って、支援していきませんかみたいな取り組みを、来年度から加速しながら進めていきたいなと思っています」
■デジタルツインは防災教育でも活用
また、『デジタルツイン』を、市民の防災に活かす動きも始まっている。和歌山県の田辺市役所では2025年2月、防災体験会が行われた。そこではデジタルツインで再現した街並みがモニターに映しだされ、ジョイスティックを使って体験していた。

カメラ付きのドローンを飛ばして市内全域をくまなく撮影し、画像をパソコンに取り込むと「デジタル田辺市」ができあがった。

田辺市は3年前にプロジェクトを立ち上げ、デジタルツインによる防災に取り組んできたが、この日初めてデジタルツインでの避難訓練を行った。
田辺市役所建設部の担当者:
「田辺市は海の近くで太平洋に面しておりまして、南海トラフ巨大地震という津波災害が非常に恐ろしいということがあるので、津波の『災害の見える化』ということ、シミュレーションに役立てられるのかなと」
田辺市は南海トラフ地震で、最大12メートルの津波が想定されている。「デジタル田辺市」でシミュレーションすると、道路や建物はたちまち水に飲みこまれた。

しかし、通ることができる道が残っているのも一目でわかる。

参加者は、コントローラーを操作しながら、津波で自分の街のどこがどう変わるのかを疑似体験した。

「ビルの何階まで水が来るのか」「どこまで逃げないと危険なのか」などを市民が自分の目で確認することで、ひとりひとりの防災意識向上に役立てていく。
訓練に参加した男性:
「自分の住んでいる場所の危険なところがわかりました。わかったり、逃げる場所も想定できるので、防災の意識を持つのにはすごくいいと思いました」
参加した別の男性:
「実体験として感じられますので素晴らしい。子供たちの好きなリモコンでできるというのが、なじみもできていいんじゃないでしょうか」
田辺市では子供たちの防災教育にも『デジタルツイン』を活用している。

田上さん:
「市民の方にこういう取り組みを知っていただくことで、市民の安心安全につながっていければ、すごくうれしいなと思います」
2025年3月12日放送